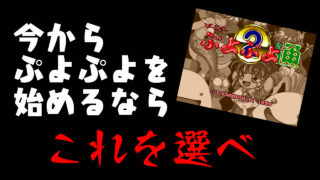 雑記
雑記 いまからぷよぷよを始める人におすすめ:ぷよぷよ通
ぷよぷよ通の魅力を徹底紹介 定期的にe-sportsが開かれるぷよぷよ。 いまやパズルゲームの代表作として名高いシリーズですがこの立場を徹底つけた原点こそがぷよぷよ通です。 一体その魅力とは何なのか。今回、解説していきたいと思います。 ...
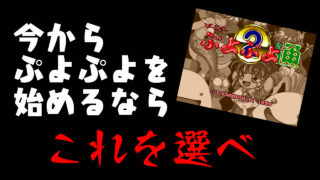 雑記
雑記  RO クエスト,イベント
RO クエスト,イベント  雑記
雑記 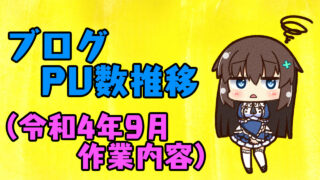 雑記
雑記  雑記
雑記  ぷよぷよ,魔導物語
ぷよぷよ,魔導物語 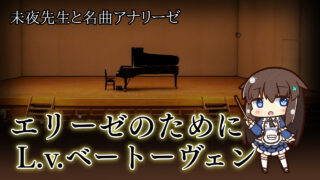 音楽解説
音楽解説  ゼロから始まるRO生活
ゼロから始まるRO生活  音楽解説
音楽解説 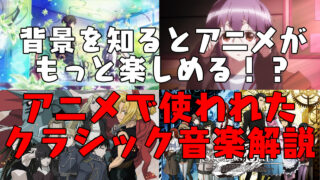 音楽解説
音楽解説