このコーナーはクラッシック音楽ができた背景や作者について解説します。
この記事を読むと以下の役に立ちます。
・クラシックについて豆知識を覚えられる
・周りからクラシックについて知っているんだなと思ってもらえる
・音楽を知っているだけでなく、作品の背景や作者の小話も話すことができ、ほんの少し人生が豊かになる
こういった音楽作品について学ぶことをアナリーゼと呼びます。
この記事では作品:第一番 ホ長調 アラベスクについて解説します。
作品の解説
クロード・ドビュッシー 第一番 ホ長調 アラベスク
この曲は、初期のピアノ作品であり、彼の作品の中では最も有名な作品の一つに数えられています。
ドビュッシーのアラベスクは第1番、第2番の2つがあり、「2つのアラベスク」として1888年に作曲され、1891年に出版されました。
第1番はスラーで流れるような曲調ですが、第2番は対照的でスタッカートが特徴のとても軽やかな曲です。
3連符で奏でられる美しいアルペジオ(分散和音)に導かれ、ロマンチシズムを感じる抒情的な旋律が紡ぎ出されます。
序盤の下降音はまるで美しい音の粒がハラハラとこぼれ落ちる情景を連想させます。
中間部に移行する前には、音階が上がりながらも抑揚がつけられており、次のメロディーを引き立たせています。
中間部では転調し、穏やかに揺れるような主題が奏でられますが、この主題は繰り返されるごとにクレッシェンド(だんだん強く)なり、risolutoの指示と共にフォルテとなり、強い印象を残します。
楽曲は再び冒頭の部分に戻り、美しいアルペジオを繰り返しながら静かに終曲します。
さて、アラベスクとは「アラビア風の」という意味で、元々はイスラム美術の装飾文様という意味でした。
植物のツルや葉、花などがモチーフとなった幾何学模様で、日本では「唐草模様」として広まり親しまれています。
ちなみに「アラベスク」というタイトルの曲を最初に作曲したのは、ロマン派の作曲家のシューマンです。
シューマンのアラベスクもまた、同じリズムの繰り返しや流れるようなメロディーが特徴です。
難易度

楽譜
解説付きクラシック動画
動画にもしているのでこちらでもどうぞ
音声あり
音声なし
こんな音楽をピアノで弾きたいあなたへ
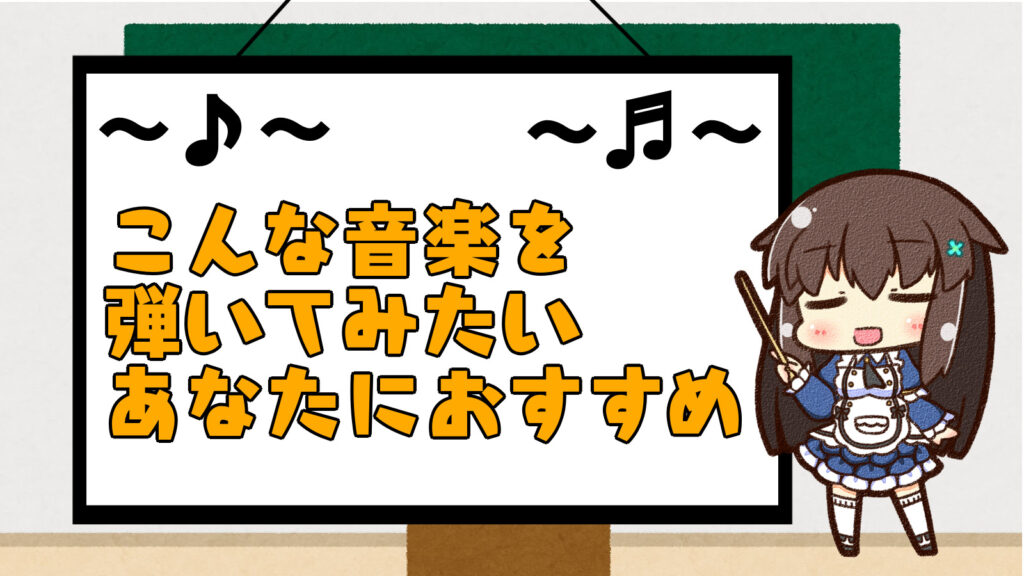
ピアノを弾きたいのであれば良い指導者のもとで練習あるのみです。
おすすめをいくつか紹介するので参考にしてください。
椿音楽教室
東京都内であればこちらがおすすめです。
1曲だけ引きたいというニーズにも対応しているため自分に合った受講ができます。
現在はオンラインレッスンも対応しています。
シアーミュージック
こちらは全国に教室があり、マンツーマンで教えてもらえる点が魅力です。
音楽は教えてもらう先生によって上達の速度が大きく変わります。
相性の良い先生から教わって一気に上達しましょう。
独学でやりたいかたにおすすめ
こちらは独学向けの方におすすめです。
初心者がピアノをマスターするのを目的に作っており、自分に合ったペースで練習できます。



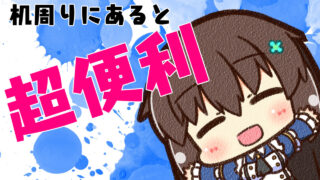



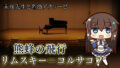
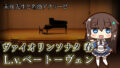
コメント