このコーナーはクラッシック音楽ができた背景や作者について解説します。
この記事を読むと以下の役に立ちます。
・クラシックについて豆知識を覚えられる
・周りからクラシックについて知っているんだなと思ってもらえる
・音楽を知っているだけでなく、作品の背景や作者の小話も話すことができ、ほんの少し人生が豊かになる
こういった音楽作品について学ぶことをアナリーゼと呼びます。
この記事では作品:舞踏への勧誘について解説します。
作品の解説
C.M.ウェーバー 舞踏への勧誘
1819年にウェーバーが妻カロリーネのために作曲した作品で、妻にこの曲を渡したとき、ウェーバーは小節ごとにその意味を説明しながらピアノで弾いて聞かせたと伝えられています。
ウィンナ・ワルツ(ワルツのタイプの一つで、主として19世紀にウィーンを中心にヨーロッパで好まれたダンス用の音楽や踊り)の雛形となった作品でもあります。
この作品によってウェーバーは「ウィンナ・ワルツの祖」と呼ばれています。
ウィンナ・ワルツの起源ともいえるこの作品は、毎年1月1日にウィーン楽友協会で行なわれるウィーンフィル・ニューイヤーコンサートでも演奏されています。
ウェーバー自身はこの曲を「華麗なロンド」とタイトルを付けていました。
しかし、この作品は、舞踏会を舞台としたドラマ的なストーリーがしばしば語られるため、「舞踏への勧誘」というタイトルの方が良く知られています。
この曲は異なる旋律を挟みながら、同じ旋律を何度も繰り返すロンド形式の曲です。
導入部はmoderato(中くらいの速さ)で、男性が女性を勧誘する場面を表現しています。
左手で主和音のアルペジオと右手がそれに応える形で導入部が終わります。
導入部が終わるとワルツのメインの部分をallegro vivace(やや速く)で演奏しています。
曲が進んでいくと、これと対比を成すかのような優雅なワルツが現れます。
この作品では、クライマックスの後に、これまでに提示したワルツを次々と回帰させる手法が用いられており、その後モデラートのコーダにより静かに曲が終わります。
主題の華やかな演奏が魅力的な作品です。
難易度

楽譜
解説付きクラシック動画
動画にもしているのでこちらでもどうぞ
音声あり
音声なし
こんな音楽をピアノで弾きたいあなたへ
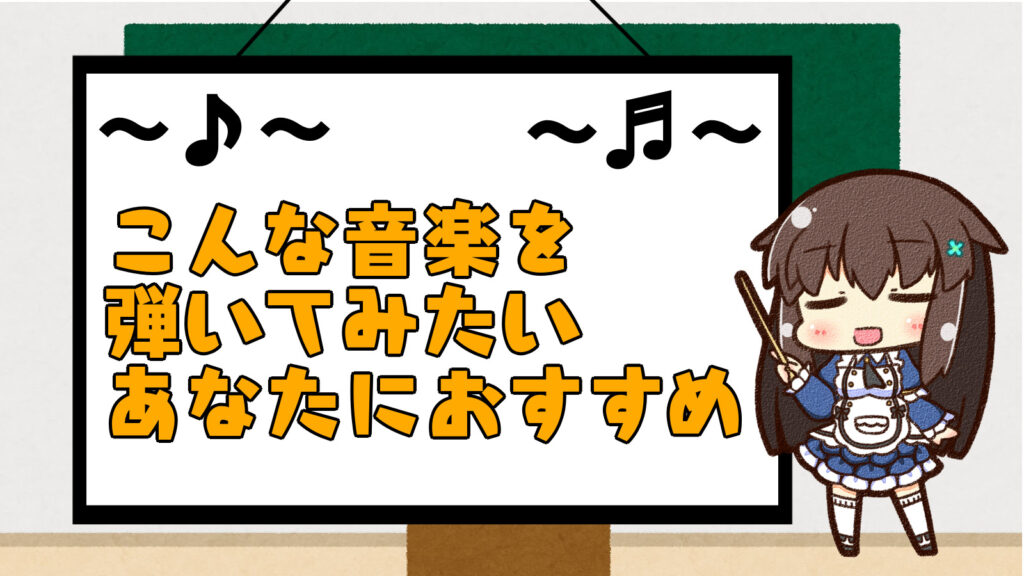
ピアノを弾きたいのであれば良い指導者のもとで練習あるのみです。
以下の記事でおすすめを紹介しているので参考にしてください。
次の記事
前の記事
関連記事



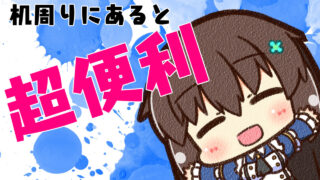



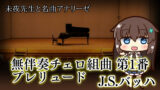



コメント